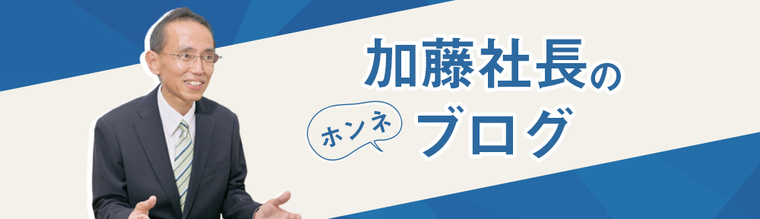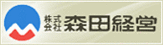2025年02月20日
「経営は継栄」 CoCo壱番屋創業者の名言
先日、CoCo壱番屋の創業者である宗次德二さんの講演会に行ってきました。
宗次さんは、1978年(昭和53年)にCoCo壱番屋を創業し、日本最大のカレーチェーン店に育て上げた方です。
講演では、ユーモアにあふれた、飾らない語り口で、宗次さんの経営に関する考え方や人生観を話されていました。
講演の中で、宗次さんが強調されていたのは、「接客第一」の姿勢でした。
宗次さんは、来店してくださるお客様を拍手でお迎えしたいくらいの気持ちで接客していた
ただ、さすがに本当に拍手でお出迎えしたらお客様もびっくりするだろうから
「笑顔で迎えて心で拍手」の気持ちでお出迎えしていたと話されていました。
また、適正な利益を出すことが健全な経営のために大切であるということを強調されていました。
バブル崩壊後の不景気でチェーン店の飲食店が軒並み値下げ競争に走ったときも
CoCo壱番屋では値下げをすることなく、接客面の向上等で業績を向上させたとのことです。
そして、今回のブログのタイトルとさせていただきましたが
宗次さんは、経営は、一時的に上手く行くだけではダメで、「継続的に繁栄」しなければならないものだと言います。
とにかくお客様に喜んでいただく、お客様にも社員にも全ての人に対して感謝の気持ちを持って働く
そうすることで右肩上がりの経営を行っていくことができる、このように話されていたのが印象に残りました。
ブログの分量の関係で割愛いたしますが、他にもためになるお話がたくさんありました。
講演会のお話に感銘を受けて、さっそく宗次さんの「経営の達人」という日めくりカレンダーを購入しました。
今年から弊社の事務所に掛け、その日の言葉を、日々の心がけとしています。
宗次さんは、現在講演を様々な機会に行われているようですので、皆様も機会がありましたら
一度宗次さんのお話を聞きに行かれてはいかがでしょうか。
間違いなく経営のヒントが得られるものと思います。
2025年01月10日
「日に新た」
明けましておめでとうございます。
この一年が皆様にとって幸多い年となりますよう祈念いたします。
さて、皆様「日に新た」という言葉をご存知でしょうか。
古代中国の殷王朝の創始者である湯王(とうおう)が、座右の銘としていた言葉とされています。
原文は「まことに日に新たなり、日に日に新たにして、また日に新たなり」というものです。
言葉の連なり自体が、躍動感をもって迫ってくるように感じます。
松下幸之助や土光敏夫、渋沢栄一といった経営者も、この言葉を好んで良く用いていました。
昨日よりも今日はより良くなろう。明日はさらに成長しよう。より良く会社を発展させていこう。
日々新たな気持ちで、新たな日を迎えたい。
このような、すがすがしい気持ち、がんばろうという気持ちにさせてくれる言葉です。
これから始まる1年を「日に新た」の心構えで過ごしていきたいと思います。
2024年12月10日
「中小企業」は減少しているのか?
一般的に「日本の中小企業の数は、毎年減少している」と思われているのではないかと思います。
この点、総務省の【経済センサス調査】によると、日本の「中小企業」の全体の数は
2012年(平成24年) 約385万社
2014年(平成26年) 約380万社
2016年(平成28年) 約357万社
2021年(令和3年) 約336万社
となっています。
これを見ると、確かに、年々、中小企業が減少しているように見えます。
ただ、「中小企業」の中から個人事業者を除いた、「中小企業のうちの会社数」の数は
2012年(平成24年) 約167万社
2014年(平成26年) 約171万社
2016年(平成28年) 約159万社
2021年(令和3年) 約174万社
となっています。
これを見ると、会社形態の中小企業の数は、約10年間で、約7万社と若干増加していることが分かります。
さらに、国税庁の【会社標本調査】によると、資本金1億円以下の「中小法人」の数は
2012年(平成24年) 約251万社
2014年(平成26年) 約259万社
2016年(平成28年) 約264万社
2021年(令和3年) 約284万社
となっています。
こちらの調査によると、「中小法人」は、約10年間で、約33万社増加しています。
国税庁の調査結果を見ると、会社数はむしろ大幅な増加傾向にあるとさえ言ってよいように思えます。
また、総務省の調査の「中小企業のうちの会社数」と国税庁の調査の「中小法人」では、
約100万社の違いがあります。
なぜ調査ごとでこのように大きな開きがあるかについてですが、2つの調査の定義の違いに理由があります。
【経済センサス調査】では、「中小企業」について、一定の場所を占めて、従業者と設備を有し、
継続的に事業活動を行っている企業と定義しています。
簡単に言うと、昭和の時代からあるような「普通の会社」をイメージしてもらうと良いと思います。
一方、国税庁の【会社標本調査】では、シンプルに、「法人税の申告書を提出した法人」全てをカウントしています。
2つの調査からは、典型的な普通の会社とは異なる、多様なかたちの起業が行われていることが窺われます。
事業形態や事業内容も多様化するなかで、【経済センサス調査】の定義では、「中小企業」を狭く捉えすぎているのかもしれません。
2024年11月11日
労働力不足社会の到来
今後の日本社会の最大の課題は、「労働力不足」です。
まず、2015年には、団塊の世代が定年退職を迎えました。
次に、2000年代から顕著になってきた少子化の進展。これにより若年労働人口が大きく減少しています。
一方で、日本人の人口が大きく減る段階には至っておらず、
社会全体での労働に対する需要(商品・サービスに対する需要)は減っていません。
これらの要因により、現在、あらゆる職種において、人手不足・労働力不足が顕在化しています。
ヒト・モノ・カネと一口にいいますが、今後は、「カネ・モノ」があったとしても、
「ヒト」がいないために、仕事ができないという事態が生じてきます。
しかも、今後少子化が解消される目処も立っていないため、
労働力不足については、時間が経てば自然に解決するというものではありません。
むしろ、少子化がますます進んでいることからすると、
今後、年数を重ねるごとに労働力不足は深刻になっていきます。
今後の企業経営においては、この「労働力不足」にどのように対応するかが極めて大きな課題となります。
2024年10月10日
ドラッカー『顧客の創造』
今月は、ドラッカーの話をしたいと思います。
”ピーター・F・ドラッカー”、経営学の巨人です。
ドラッカーは膨大な著作を遺していますが、主著を上げるなら『マネジメント』でしょう。今から5~6年前、私が森田経営に入る2~3年ほど前のことですが、
森田経営の創業者である森田勝己さんと、このような会話をしたことがありました。
森田「西川さんは、経営にご関心はありますか」
西川「興味ありますよ。ドラッカーの『マネジメント』は好きで、何度も読み返しています」
森田「そうですか!私もドラッカー好きなんですよ。
ドラッカーのいう『顧客の創造』が経営者の永遠の課題です」
森田勝己さんは、私の妻の伯父になります。この会話をした2~3年後に森田勝己さんが亡くなられ
勝己さんの死を機に、私は森田経営に入ることにしました。
森田勝己さんの発言にあった『顧客の創造』、これはドラッカーの言葉の中で最も有名な言葉だと思います。
「企業の目的は、顧客の創造である」
『マネジメント』の冒頭に出てくる言葉で、簡潔で含蓄のある力強い言葉です。
具体的にいえば、新規顧客の獲得、獲得した顧客の定着、潜在需要の掘り起こし、新市場の開拓などを
指すものと思いますが、それだけに留まらない、より深い意味の広がりを感じさせる言葉です。
私が初めてドラッカーを読んだのは、今から10年ほど前になりますが
そのとき覚えた感動は今も覚えています。
ドラッカーの尽きない魅力について、今後もお伝えしていきたいと思います。
- キーワード検索

西川 和志
税理士法人 森田経営
代表社員
昭和54年7月19日生
主な資格:税理士、弁護士
- カレンダー
- 月別の日記一覧
-
- 2025年12月 (1)
- 2025年11月 (1)
- 2025年10月 (1)
- 2025年09月 (1)
- 2025年08月 (1)
- 2025年07月 (1)
- 2025年06月 (1)
- 2025年05月 (1)
- 2025年04月 (1)
- 2025年03月 (1)
- 2025年02月 (1)
- 2025年01月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年09月 (1)
- 2024年08月 (1)
- 2024年07月 (1)
- 2024年06月 (1)
- 2024年05月 (1)
- 2024年04月 (1)
- 2024年02月 (1)
- 2024年01月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (1)
- 2023年09月 (1)
- 2023年08月 (1)
- 2023年07月 (1)
- 2023年06月 (1)
- 2023年05月 (1)
- 2023年04月 (1)
- 2023年03月 (1)
- 2023年02月 (1)
- 2023年01月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年11月 (1)
- 2022年10月 (1)
- 2022年09月 (1)
- 2022年08月 (1)
- 2022年07月 (1)
- 2022年06月 (1)
- 2022年05月 (1)
- 2022年04月 (1)
- 2022年03月 (1)
- 2022年02月 (1)
- 2022年01月 (1)
- 2021年12月 (1)
- 2021年11月 (1)
- 2021年10月 (1)
- 2021年09月 (1)
- 2021年08月 (1)
- 2021年07月 (1)
- 2021年06月 (1)
- 2021年05月 (1)
- 2021年04月 (1)
- 2021年03月 (1)
- 2021年02月 (1)
- 2021年01月 (1)
- 2020年12月 (1)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (1)
- 2020年09月 (1)
- 2020年08月 (1)
- 2020年07月 (1)
- 2020年06月 (1)
- 2020年05月 (1)
- 2020年04月 (1)
- 2020年03月 (1)
- 2020年02月 (1)
- 2020年01月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年09月 (1)
- 2019年08月 (1)
- 2019年07月 (1)
- 2019年06月 (1)
- 2019年05月 (1)
- 2019年04月 (1)
- 2019年03月 (1)
- 2019年02月 (1)
- 2019年01月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年10月 (1)
- 2018年09月 (1)
- 2018年07月 (1)
- 2018年06月 (1)
- 2018年05月 (1)
- 2018年04月 (1)
- 2018年03月 (1)
- 2018年02月 (1)
- 2018年01月 (1)
- 2017年12月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年09月 (1)
- 2017年08月 (1)
- 2017年07月 (1)
- 2017年06月 (1)
- 2017年05月 (1)
- 2017年04月 (1)
- 2017年03月 (1)
- 2017年02月 (1)
- 2017年01月 (1)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年10月 (1)
- 2016年09月 (1)
- 2016年08月 (1)
- 2016年07月 (1)
- 2016年06月 (1)
- 2016年05月 (1)
- 2016年04月 (1)
- 2016年03月 (1)
- 2016年02月 (1)
- 2016年01月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年09月 (1)
- 2015年08月 (1)
- 2015年07月 (1)
- 2015年06月 (1)
- 2015年05月 (1)
- 2015年04月 (1)
- 2015年03月 (1)
- 2015年02月 (1)
- 2015年01月 (1)
- 2014年12月 (1)
- 2014年11月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年09月 (1)
- 2014年08月 (1)
- 2014年07月 (1)
- 2014年06月 (1)
- 2014年05月 (1)
- 2014年04月 (1)
- 2014年03月 (1)
- 2014年02月 (1)
- 2013年12月 (1)
- 2013年11月 (1)
- 2013年10月 (1)
- 2013年09月 (1)
- 2013年08月 (1)
- 2013年07月 (1)
- 2013年06月 (1)
- 2013年05月 (1)
- 2013年04月 (1)
- 2013年03月 (1)
- 2013年02月 (1)
- 2013年01月 (1)
- 2012年12月 (1)
- 2012年11月 (1)
- 2012年10月 (1)
- 2012年09月 (1)
- 2012年08月 (1)
- 2012年07月 (1)
- 2012年06月 (1)
- 2012年05月 (1)
- 2012年04月 (1)
- 2012年03月 (1)
- 2012年02月 (1)
- 2012年01月 (1)
- 2011年12月 (1)
- 2011年11月 (1)
- 2011年10月 (1)
- 2011年09月 (1)
- 2011年08月 (1)
- 2011年07月 (1)
- 2011年06月 (1)
- 2011年05月 (1)
- 2011年04月 (1)
- 2011年03月 (1)
- 2011年02月 (1)
- 2011年01月 (1)
- 2010年12月 (1)
- 2010年11月 (1)
- 2010年10月 (1)
- 2010年09月 (1)
- 2010年08月 (1)
- 2010年07月 (1)
- 2010年06月 (1)
- 2010年05月 (1)
- 2010年04月 (1)
- 2010年03月 (1)
- 2010年02月 (1)
- 2010年01月 (1)
- 2009年12月 (1)
- 2009年11月 (1)
- 2009年10月 (1)
- 2009年09月 (1)
- 2009年08月 (1)
- 2009年07月 (1)
- 2009年06月 (1)
- 2009年05月 (1)
- 2009年03月 (1)
- 2007年09月 (1)
- 2007年07月 (1)
- 2007年06月 (1)
- 2007年05月 (1)
- 2007年04月 (1)
- 2007年03月 (1)
- 2007年02月 (1)
- 2007年01月 (1)
- 2006年12月 (1)
- 2006年11月 (1)
- 2006年09月 (1)
- 2006年08月 (1)
- 2006年07月 (1)
- 2006年06月 (1)
- 2006年05月 (1)
- 2006年04月 (1)
- 2006年03月 (1)
- 2006年02月 (1)
- 2006年01月 (1)
- 2004年11月 (1)
- 2004年09月 (1)
- 2004年06月 (1)
- 2004年02月 (1)
- 2003年11月 (1)
- 2003年01月 (1)
- 2002年07月 (1)
- 2002年01月 (1)
- タグ一覧